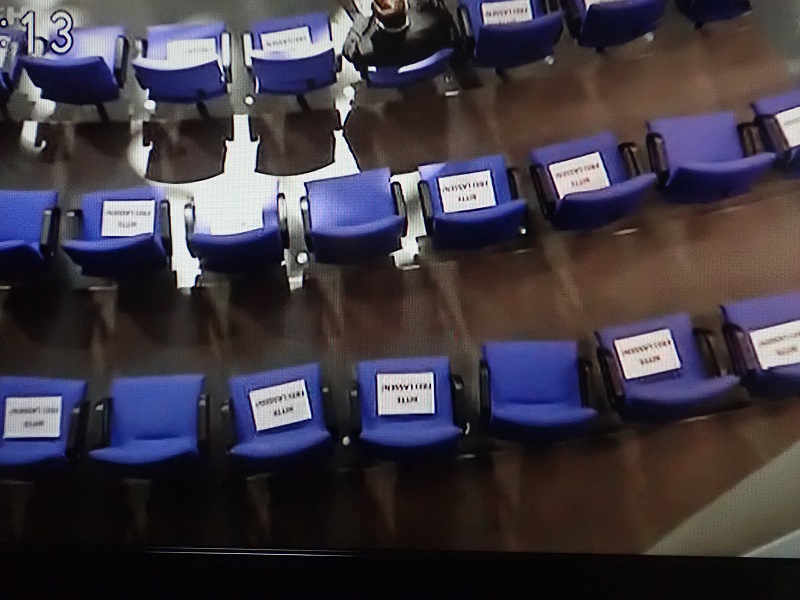「コロナ危機」が深刻さを増している。3月9日、私は、「五大陸すべてに感染が広がっている。日本で本格的なPCR検査が行われるようになれば、感染者数の桁が変わってくるだろう。特にオリンピック会場のある東京都において。」と書いた(直言「安倍首相に「緊急事態」対処を委ねる危うさ―「水際」と「瀬戸際」の迷走」)。「新型コロナの大感染がすでにこの国に存在しているのに、「五輪面子(めんつ)」で隠蔽している安倍政権」(直言「「幻の東京五輪」再び―フクシマ後9年、チェルノブイリ後34年の視点」)の「不都合な真実」について、米国は了解済みだったのではないか。いよいよ日本、特に東京が危ない。
「アベノマスク」政策に米国人、日本脱出
在日米国大使館は4月3日、「健康警報」(ヘルス・アラート)を出して、日本における急速な感染拡大に警鐘を鳴らし、米国市民に即時帰国(immediate return)準備を呼びかけた。欧米に比べて日本の感染者数の報告が少ないことを挙げ、「広範な検査をしないという日本政府の決定は、COVID-19の感染率を正確に把握することを困難にしている」と明確に指摘している。2011年の福島原発事故以来の「日本脱出」対応である。
「コロナ危機」は、各国の首脳や政府のレベルがはっきりわかってしまう「試験」のような働きをしているように思う。感染に苦しむそれぞれの国で、誰が、どのような形で国民の前に立っているか。BS1の「ワールドニュース」をいつも録画してみているが、2月以降、その時間が格段に増えた。
9月1日の「防災の日」にはわざとらしい防災服を着る安倍首相は、この間、いつも高級スーツで登場する。本部長がこれだから、閣僚も「平時モード」で対策本部に緊迫感はない(東日本大震災の時は首相も閣僚も防災服だった)。その安倍首相が先週から唐突に布製マスクをしはじめ、対策本部も全員がマスク姿になった。それにしても、「私が決断した以上は」と息巻き、「躊躇なく」「断固として」「先手、先手で」「前例のない」対策を打ち出すと宣言しながら、やったことと言えば、補償もなしの思い付きのイベント自粛要請(2月26日)や全国一斉休校要請(27日)だった。すでに紹介したように、スポーツ紙にまで「コロコロコロナ対策 国民怒り沸騰」と茶化されるほどだった。
そこへきて、4月1日、これまた唐突に、「一世帯2枚のマスク」を5000万世帯に郵送すると宣言したのである。「アベノミクス」から「アベノマスク」へ。これを皮肉る『日刊ゲンダイ』4月4日付。麻生太郎財務大臣の「ぶら下がりマスク」姿(是非、クリックしてください!)を見て、必死にマスクを確保しようとしている医療関係者や市民はどう思うだろうか。マスク(しかも布マスク)2枚なんて、一体誰のアイデアなのか。『朝日新聞』4月3日付によれば、「経済官庁出身の官邸官僚」が「全国民は布マスクを配れば、不安はパッと消えますから」と進言。安倍首相が飛びついたようである。3月27日の全国一斉休校を文科大臣に相談もせずに首相に決断させたのは今井尚哉首相補佐官だったから、『朝日』は名指しこそしていないが、その「官邸官僚」は今井補佐官なのかもしれない(『週刊新潮』4月23日号(4月 16日発売)によると、その「官邸官僚」は経産省出身の佐伯耕三秘書官だとい う:4月16日追記)。首相動静欄を観察していると、合計時間は数えたことはないが、毎日最もよく会っているのが、今井補佐官と、詩織さん事件もみけしの黒幕、北村滋国家安全保障局長(内閣特別顧問)の2人である。高度の医学的・疫学的知識を必要とする「コロナ危機」対処を、「高尾山登山メンバー」の経産官僚と警察官僚に過度に依存している安倍首相の舵取りの危うさを思う。
「私が決断した以上は」と一人で仕切ろうとする自意識過剰の安倍首相と異なり、各国首脳は専門家を両側に、あるいは背後に控えさせて、記者の質問に答えようとする。小池東京都知事の記者会見の方が、知事の政治判断と専門家の医学的・疫学的判断とを区別して質問に答えていたので、その限りで分かりやすかった。国の基本方針では首脳が前面に出てきて、細かなことは閣僚や専門家にまかせる。ところが、「マスク2枚」なんて、局長クラスの話を首相が記者会見で、あるいは本会議の壇上から胸をはって言ってしまう。脱力続きの話はこのくらいにして、ここでドイツの先週の動きを見てみよう。
ドイツで「緊急議会」の提案――基本法改正?
ドイツ政府は、先月25日の連邦議会において大規模な「コロナ危機」救済プログラム(「ドイツのためのコロナ保護シールド」)が決定されてから、イベント自粛などで仕事を失った人などに、ほとんど審査なしで5000ユーロ(約60万円)を配り、また中小・自営業者などへの緊急援助に500億ユーロ(約6兆円)の、返済不要の補助金を支給した。非課税世帯30万円だのといっている安倍政権とは桁も、中身も、気っ風も大違いである。
前回の「直言」では、ドイツ感染防護法の改正法が、「コロナ危機」に対処するという緊急性や必要性にもかかわらず、重大な憲法問題をはらんでいることを紹介した。主な論点は、基本法83条により州の固有事務とされている連邦法律の執行が、連邦省それ自体に委ねられることを普通の法律でやってしまったこと。本来ならば、このような権限配分には、基本法(憲法)改正が必要だった。また、行政機関の法規命令について、連邦参議院の同意なしに授権していることである。新型コロナの感染防止という緊急の必要性が一人歩きして、議会の後退が著しい。こうした問題への危機感は、なかなか共有されにくいだろう。「憲法学者が細かな手続き論をいっている。いまはそんな場合ではない」という主張は、いずこにおいても一般受けしやすいからである。
ヴォルフガング・ショイブレ連邦議会議長。ドイツ統一時の連邦内務大臣で、22年前にベルリンで偶然遭遇し、「眼光鋭い、保守の知性派」と書いたことがある。基本法改正に熱心な政治家であり、テロ対策のための連邦軍の国内出動を可能にする基本法改正を主張したこともある(直言「憲法は究極の「岩盤規制」」)。そのショイブレ議長が、4月2日、議会の全会派に対して、「緊急議会」(Notparlament)の方式を提案した(「コロナ危機―連邦議会のための救援パッケージ(Rettungspaket)」(『南ドイツ新聞』デジタル4月3日)。議会の行為能力が危殆に瀕しているという認識のもと、2つの可能性、すなわち「ミニ緊急議会」と「ヴァーチャル議会」を提案する。
先週の「直言」で写真を使って紹介したように、先月25日の連邦議会は、議席の間を2つあけて議員が着席したため、4分の1の議員を各会派の議席割合で「間引き」して開催した。ちなみち、日本の国会は、総議員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができないが(日本国憲法56条)、ドイツ基本法にはこの定足数の規定がない。議員の過半数が議場に出席していることが議決の前提となっている(議事規則45条1項)。その意味では、ドイツの方が「定足数」が厳格といえる。だから、「コロナ危機」で多数の議員が議場にいないと審議も議決もできないというのは具合が悪い。そこでショイブレ議長は、対外的緊急事態である「防衛事態」(外部からの武力攻撃)の場合、48人のメンバーからなる「合同委員会」という「ミニ緊急議会」の仕組み(基本法53a条)を「コロナ危機」において設置することを提唱したわけである。基本法上、「合同委員会」は、外部からの武力攻撃という「防衛事態」(115a条) という戦時において作動し(115e条)、大規模自然災害やパンデミックには適用がない。ショイブレ議長の主張は当然、基本法(憲法)改正の問題に連動する。なお、この写真は、ボン近郊にあった政府核シェルター(正式名称は「連邦憲法諸機関退避所」(AdVB))内の「合同委員会」が開かれる部屋である(直言「再訪・政府核シェルター―緊急事態法の「現場」へ(その2)」の中程参照)。
もう一つの可能性は、電子投票の仕組みである。議会主義は投票以上のもので、議論から成り立っている。後者を電子的に確保することはむずかしい。こういう認識から、ショイブレの提案の重点は「ミニ緊急議会」に傾く。ただ、この「緊急議会」も常に物理的に会合する必要があり、感染のリスクもある。一方、少数の病気の議員でさえも、選挙で選ばれた議員であり、その意見を反映しない過半数となる可能性をどう考えるかという難問もある。議会のどの会派も提案に批判的であり、基本法改正を含む議長の「緊急議会」の提案が実現する見通しはない。ショイブレの基本法改正の試みは、またも失敗したようだ。ただ、こういう議論が先週末にドイツで出てきて、基本法(憲法)改正の論点になっていることは、日本の改憲論議と重なる論点(大規模災害時の議員任期延長)もあるので留意しておきたい。
「戦時でさえ基本権は損なわれない」――ドイツ連邦憲法裁判所前長官の批判
次に、市民の視点からみれば、「コロナ危機」においては、途方もなく自由や権利を制約されているわけで、「自粛」という名の半強制も働いている。「コロナの前に憲法は停止するのか」という際どい問題が投げかけられている。この写真は、「9.11」6周年の『シュピーゲル』誌(2007年9月7日号)の表紙である。正義の女神が自爆テロのダイナマイトを腹に巻いて、導火線に火もついている。その前に置いてあるのは、ボンの古道具屋で購入した「正義の女神」座像である。「法治国家の自爆」にならないように、「コロナ危機」にも冷静に対応する必要がある。
そういう時、『南ドイツ新聞』4月2日付は、「コロナ危機と基本権」というテーマ特集(デジタル版は「民主主義」) で、ドイツ連邦憲法裁判所のハンス=ユルゲン・パーピア前長官(76歳)のインタビューを掲載した(冒頭左の写真がその2面の記事)。タイトルは、「ならば、自由主義的法治国家は退いた」。デジタル版4月1日18時59分のタイトルは「戦時でさえ基本権は損なわれない」(Selbst in Kriegszeiten werden die Grundrechte nicht angetastet)という、いずれも刺激的なもの。リード文には、「私は全体的監視国家への傾向に対して警告する」「日常の多くの制限がより長期にわたって続くならば、自由は危機に瀕する」とある。パーピア前長官は、監視国家を警告し、集中治療患者の選別についての医師のための勧告(後述)を「非常に危険」と批判する。
1998年から連邦憲法裁判所の裁判官となり、2002年から2010年まで長官を務めた。テロリストにハイジャックされた航空機を撃墜することを認めた航空安全法14条を憲法違反とする判決にも、第1法廷裁判長として関わった(直言「「ハイジャック機撃墜法」の違憲判決」参照)。ドイツで最も知られた国法学者(憲法学者)の一人でもある。
インタビューで記者は、いま大規模な基本権制限を受けて生活しているドイツ人の95%がこれを肯定している事実について触れ、法治国家の現状について懸念はないかと質問する。これに対して前長官は、「法治国家は、このような危機においても、行為能力も生き残る能力も持たねばならないので、私は長期的には心配していない。しかし、必要の前に法なし(Not kennt kein Gebot)と考えてはならない。それは法治国家の終わりだろう。」と述べて、具体的にどのようなところに危険を見出すのかと記者に問われて、感染防護法の定める「必要な保護措置」について立ち入る。「危険の真の程度と、そこでとられる措置の適合性と必要性について、なお不確実である」という点に着目しつつ、ただ、感染症に関する危険性の知見が十分でないので、外出制限が比例性を欠くとまではいえないと述べ、これを一つのジレンマだと前長官はいう。したがって、当該措置が基本権に対する重大な侵害になっても、目下のところ法的異議を申し立てることはできないことになるという。
「コロナ危機」においては、広域にわたる要請や禁止は、国内のすべての人々に感染の疑いがあり得るということを前提としている。これは現時点では変わりはないが、長期的には適用できないし、危険の態様や程度をより正確に定義するために、あらゆる努力が必要となる。政治や行政は、個々具体的なより制限的でない措置があるかどうかを繰り返し審査する必要がある。長期的には、かかる包括的な制限は容認できず、一時的なものでなければならない。
この前長官の指摘に対して記者は、しかし、専門家[コロナ対処を仕切るRKI(ローベルト・コッホ研究所)]ですら措置の有効性はわからない、と踏み込む。前長官は、より多くの検査や医療機器の不足の問題を挙げながら、それを理由として、「あらゆる者の自由を長期的に極端に侵害したまま、人々の自由を深刻に侵害しない他の手段を提供することができなかった場合、致命的であろう」として、そこに「法治国家の侵蝕(Erosion)の回避可能な危険」を見てとる。では、「法治国家の侵蝕」はどこにあるのかと問われて、短期的には問題はないが、長い間続くならば、自由主義的法治国家は退く。これは防ぐ必要がある。外出制限の措置をいつ終わらせるのか決定するのは、政治と行政だが、法治国家は、その政治や行政が独立した裁判所によって統制されていることを意味する、と。
記者は、外出制限に反対するデモが2メートルの間隔をあけて行われた場合はどうかとか、財産権や職業選択の自由といった経済的な基本権との関係、補償の問題などについて立て続けに質問していく。前長官は特に、感染防護法の補償規定の不十分な点と、その改正の必要性にも言及するが、省略する。
このインタビューで注目されるのは、基本法上、防衛事態(外部からの武力攻撃)における緊急事態規定は存在するが、パンデミックにはないということである。「戦時においてさえ、基本権は損なわれることはなく、連邦憲法裁判所の権限も侵されない[基本法115g条]」。このことは、目下の「コロナ危機」においても妥当する。その意味で、医師や看護師に特定の業務を義務づけるノルトライン=ヴェストファーレン州エピデミック法の草案は疑問であるとする。基本法12条は、「何人も、・・・特定の労働を強制されてはならない」と規定している。
それ以外の面で変化したことを問われて、連邦主義の軟化であるという。連邦への権限集中のなかで州の権限の問題である。これについては省略する(先週のクリストフ・メラース教授のインタビュー参照参照)。
記者は、長く裁判官を務めたパーピア前長官に対して、この危機のなかで司法の独立にこだわるのかと挑発的な質問を向ける。前長官は、人身の自由〔ここでは行動の自由〕が非常に重要であっても、生命と健康の保護を軽視する責任を取ることはできないと言ったある裁判官を想起し、この裁判官は、政治や行政が直面しているのと同様に、危険の態様と程度、ならびに手段の適合性と必要性に関する不確実性に直面していると語る。
記者はさらに、中絶や強制ワクチン接種の問題で問われた、国家による生命の保護の問題に踏み込んだ質問を続ける。前長官は、現時点では、十分な集中治療室を持っていない場合、人々がどのように扱われるかが非常に危惧されるとして、これは倫理的な観点から議論されているが、それはまた法的な問題でもあると指摘する。
補足しておくと、ここで前長官が問題視した「勧告」とは、3月25日、「COVID-19パンデミックにおける救急・集中治療資源の分配の決定に関する勧告」のことで、ドイツ集中救急医学学会(DIVI)やドイツ麻酔科・集中治療医学会(DGAI)など7つの専門学会によって出された。それによると、以下のような場合、人工呼吸器を使った集中治療は行われない。(1)死への過程が絶え間なく開始されたこと、(2)治療が医学的に見込みなしと評価されること(改善または安定化が期待できない)、(3)生存することが、集中治療室にかなり長期にわたり滞在することと結びつくこと、(4)患者がそのような治療を拒否していること(例えば、患者の指示や従前の口頭による表明、あるいは患者の推定意志によって)。
安楽死などの基準に近いものだが、違うのは集中治療室と人工呼吸器が足りないという医療的リソースの問題が条件に含まれていることである。端的に言えば、90歳の患者と30歳の患者がいて、人工呼吸器が1台しかないという場合の「医療資源の配分」の問題だが、ダイレクトに「命の選択」、トリアージにつながる。この問題について前長官は、この勧告は、「人間の尊厳」(基本法1条1項)と「人間の尊厳」保護の平等の原則の観点から疑問であり、法的に問題があると断定する。
これに対して、記者は、テロリストによって乗っ取られた旅客機を、他の場所での被害を防ぐために撃墜することが許されるべきかという問題にあえて立ち入る。前長官が裁判長として関わった航空安全法違憲判決を念頭に置いた質問である。前長官は、「いかなる生命も等しく、同じく価値がある」として、盲目的にこの勧告に従わないことを医師に助言することはできるという。結局のところ、それは過失致死(刑法222条)で告発される可能性がある。記者は納得せず、複数の患者が人工呼吸器を競うことになった場合、集中治療室に到着の順番で決まるのかなど、息詰まるやりとりが続く。前長官は、「この人は、遅かれ早かれ、すでに死を運命づけられている」というモットーに従った衡量では、「人間の尊厳」保障と相容れない。結局のところ、治療を決めるのは常に医師であり、勧告は、刑事訴訟の場合に医師の正当化根拠とはならないという。
記者は、「コロナ危機」におけるもう一つの難題に質問を向ける。それは、感染者を監視するさまざまな装置や仕組みの問題である。中国や韓国を念頭に置いた質問だが、前長官は、ここドイツでは、それはプライバシーの基本権と情報自己決定権を侵害するとして、行動識別ファイルを包括的に作成して評価することになると、許容の限界を超えている、と指摘する。これはドイツ連邦憲法裁判所の判例を基礎に置いた回答といえる。
記者はドイツで議論されているモデルについて前長官の意見を求める。携帯電話の位置情報を利用した感染情報の警告の問題である。前長官は、それがあくまで自発的であり、匿名のままである限りは法的に問題ないとするが、記者は、国家がそのモデルを市民に義務づけるような場合は、一般的な外出禁止におけるよりも小さい基本権侵害になるのかと突っ込む。前長官は、それが強制的に行われれば、いつの間にかほとんどすべてが把握され、行動識別ファイルがそれらを介して作成され、包括的な位置情報の調査が可能になるから、一度それをやれば取り除くことはできなくなり、その後、我々は完全に監視された社会にいることになる。最初は魅力的に聞こえるので、外出を禁止するよりもまだ良いように思えるが、として、前長官は、全体的監視国家への傾向に警告を発している。
ドイツ司法の頂点に12年もいた憲法学者でも、「コロナ危機」にいかに向き合うかということには法律家としては難しい問題が多く、必ずしも歯切れがよいわけではない。新たなウイルスによって引き起こされた緊急事態には、どんな指導者も、医療や感染症の専門家も、日々悩みながら対応しているわけで、連邦憲法裁判所前長官のインタビューから学ぶことは、原因がまだ不明のウイルスが相手でも、法治国家の原則にしっかり立ち続けるということである。「今回だけは例外だ」という言葉を吐いて、指導者が暴走するようなことがないように、立ち止まって考え、事後的検証のための記録をきちんと保存し、将来の新たな危機に備えることが求められるのである。その点で、日本の場合は、最悪な状況に、最悪の政権が対応しているということになる。
「憲法学者がとにかく嫌い」という安倍首相や、それを支える大メディア。この大惨事に便乗した改憲の危険に注意を怠ってはならない。
感染爆発がすでに起きているのに、「まだ持ちこたえている」「ぎりぎりの瀬戸際」といった曖昧な表現で「寸止め」にしている首相の狙い通り、医師会や普通の市民から「早く緊急事態宣言を出してほしい」という声が挙がっている。この「寸止め戦略」は、緊急事態宣言を出したあとの自分たちの責任問題を回避するためにも、形の上で、「緊急事態宣言を!都市封鎖を!」といった市民の声にこたえたのだ、という形を残したいのだと思う。市民の要望に押された形で強権発動に踏み切る。そして、本来、2012年法の解釈・運用で可能だったものを、32条(緊急事態宣言)を前面に押し出した「安倍バージョンの特措法」をあえて制定したのも、「国民に慣れてもらう」ということにほかならない。まさに「憲法改正の大きな実験台」である。
いま、一人ひとりにとって正念場である。私の大学も完全オンライン教育に踏み切る決断をした。いま、私自身、自宅にこもりながら、春学期の800人近い学生たちにどのような授業ができるか苦闘している。研究室の院生たちと来週から、オンラインで「研究会」を実施する準備が整った。命を守りながら、生活を続ける。命を守りながら研究・教育を続ける。