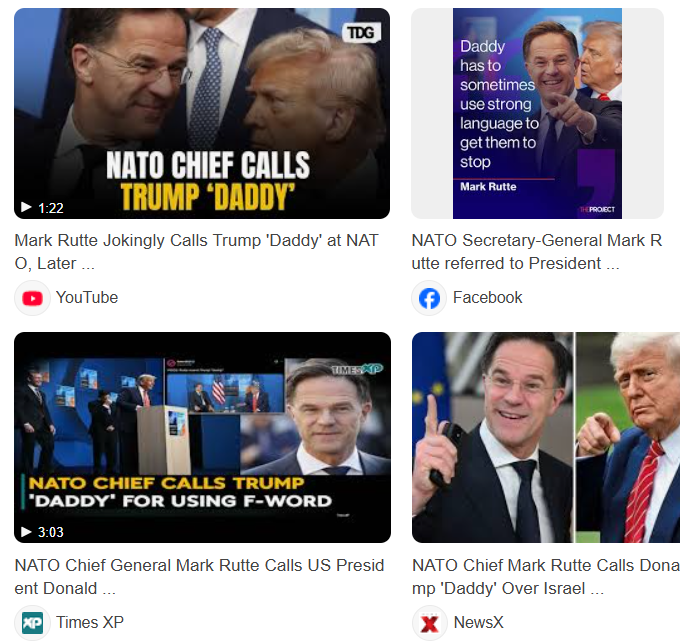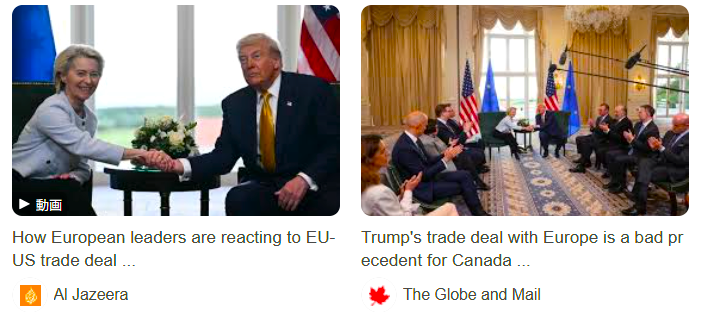「世界の地上げ屋」に媚びるのか―― トランプとNATO・EU、日本…
2025年8月8日

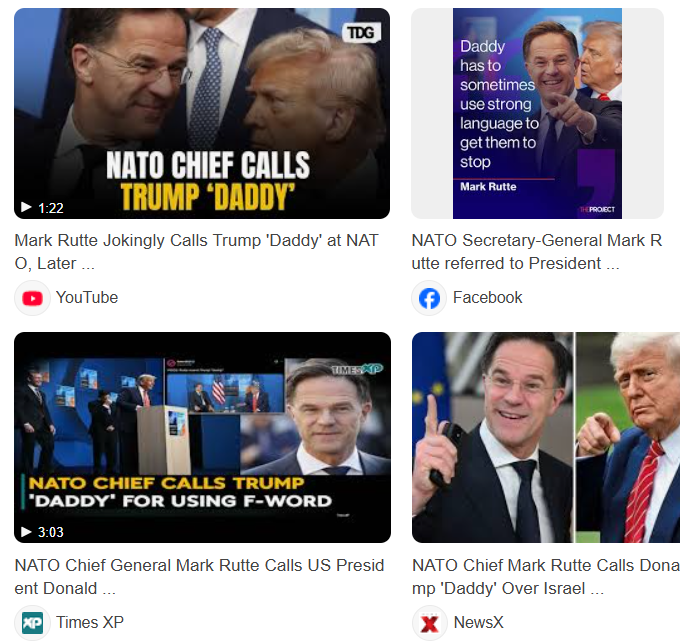
「トランプ2.0」の200日―MAGAとTACOの関係
1月20日から今日(8月8日)で200日になる。「トランプ2.0」(「アメリカ・ファースト」・米国第一主義)によって、世界中がいいように振り回されている。トランプの行動様式は“TACO”といわれている。“Trump Always Chickens Out”(トランプはいつもビビッて退く)の頭文字を取った略語。「今だけ、金だけ、米国(自分と岩盤支持層)だけ」の思いつきで動き、反発が強いとみるや、すぐに変更・撤回する。恥も外聞もなく。そこには、「ディール」という企業の合併・買収や不動産屋の「地上げ」的な発想が貫かれている。他方、彼が最も気にするのは、岩盤支持層(MAGA)の気分と意向である。
実際、2025年に入ってからのトランプの動きは、世界秩序に対するアメリカの関与のあり方を大きく変えるものとなった。突然の強硬(あるいは柔軟)姿勢や劇的な方針転換は、国際機関の活動を停滞させ、国際社会に不安と緊張をもたらしている。特に安全保障分野では、「同盟国」への負担増加や新たな防衛戦略の構築が求められるなど、各国はあたふたと対応を迫られている(直言「トランプの平和」(Pax Trump)と「ウクライナ戦争」─NATOの終わりの始まり?」参照)。
思えば、冷戦が終わり、90年代から2010年代までは、「不確実性」や「不安定性」が安全保障上の脅威の基礎に置かれ、膨大な兵器購入の根拠とされた。2014年以降はロシア、そして中国が脅威とされてきたが、実は現時点での最大の「不安定要因」、すなわち「脅威」は、トランプ政権下の米国ではないだろうか。
「ヒロシマ・ナガサキ80年」にイラン核施設を「空爆」
6月22日(日本時間)、トランプは、イランの核施設をバンカーバスター(地中貫通爆弾)によって破壊するという暴挙に出た。これについては「米国第一主義」と整合する軍事介入なのか疑問である。ただ、この核施設攻撃には、イランとの関係を一気に悪化させないための微妙な手加減(ディールの手段?)があったのではないか。核施設の被害状況を含めて、米国とイランの双方が詳細を明らかにしていないのも不可解である。
イラン核施設「空爆」の翌週のドイツ週刊誌Der Spiegel(Nr.27, 27.06.2025)の表紙は、「世界の警察官」の制服でふんぞりかえるトランプのイラストである(冒頭の写真)。副題は「イスラエル、イラン、NATO―トランプの新たな権力誇示の背後に何があるか」。トランプが唐突にかつてのアメリカの役割(「世界の警察官」)を受け入れたかのように見えるが、平和は決して彼の得意分野でなかったことを論じていく。
2013年、民主党のバラク・オバマでさえ「米国は世界の警察官ではない」と明言し、軍事介入への消極姿勢を示したのだから、ましてや、米国第一主義(アメリカ・ファースト)のトランプが、「世界の警察官」を目指すとは考えられない。
ハル・ブランズ(ジョンズ・ホプキンス大学)はForeign Affairs (2025年2月25日)において興味深い指摘をしている。「ドナルド・トランプはアメリカの政治秩序を一変させた。…トランプは、危機に瀕したアメリカの秩序を守る理想的な擁護者ではない。…トランプは強硬なナショナリストであり、権力、利益、一方的な優位性を追求する。…彼の地政学的傾向は変わっておらず、反民主主義的傾向は悪化の一途をたどっている。彼の掲げる「米国第一主義」は、敵味方、そしてその間にいるすべての人を対象とした、峻厳で全方位的なナショナリズムを依然として特徴としている。…」(前掲・直言より)。
トランプは、「世界の警察官」としての機能・役割、人員、費用をヨーロッパや日本に担わせようとしているが、それはまずNATOを恫喝するところから始まった。

NATO、トランプにひれ伏す―国防費「GDP5%」の合意と含意
6月25日にハーグで開催されたNATO首脳会議で、マルク・ルッテNATO事務総長(オランダ元首相)がトランプのことを「ダディ(Daddy)」と呼んで世界を驚かせた、というよりあきれさせた(冒頭の写真参照)。NATOのトップがここまでトランプに卑屈になるのかと驚くばかりだった。結局、加盟する32カ国は、国防費を国内総生産(GDP)の5%に引き上げることで合意したとされる。ただ、その内実は従来のGDP
3.5%に、テロ対策や軍事利用可能なインフラ(鉄道、港湾、橋など)への支出の1.5%を加えるという「政治的数字」といえるものである。目標の達成期限も「2035年」とされているから、トランプ政権が来年11月3日の中間選挙で民主党に破れて不安定化するとにらんで、「手抜き」は折り込み済みというところだろうか。
事務総長が「ダディ、トランプ」と呼びかけるほど、NATOはトランプの前にたじたじである。ロシアのメディアから、「最近のNATO首脳会議は、過去最高額をかけることになる屈辱的な倒錯劇だった」と酷評されるほどである(RT 2025年6月26日)。いわく。「…2030 年のロシア侵攻という仮定のもと、ヨーロッパの納税者に大量の米国製および欧州製の軍事装備品の購入を強要する。散財のための完璧な口実だ。放火犯に自分の火を消してくれたことへの感謝の気持ちとは何と素晴らしいことか。トランプを年間最優秀消防士にノミネートするのか?」と痛烈である。
スペインの首相がGDP 2%の維持を明言する一方、ポーランド大統領は5%の支出目標を「紳士協定」と呼び、まともに守る気がない。もともと従う気のないハンガリーのオルバン首相は、ウクライナのゼレンスキーがNATO会議に参加していないことをもって、「これまでの時代は終わった」と述べている。
それにしても、この首脳会議の2日前に行われたイラン核施設への攻撃について、事務総長のルッテは、「国際法に違反していない」と断定した。NATO条約1条は「国際関係において国際連合の目的に合わないあらゆる手段による武力の行使を行わない」としており、自衛権の行使でもないむき出しの武力行使を、ここまで卑屈に正当化するNATO事務総長の姿勢には驚くばかりである。
「憲法ブログ」(verfassungsblog.de) において、マティアス・クム(ニューヨーク大学、ベルリン・フンボルト大学)は、「国際司法裁判所(ICJ)と国際刑事裁判所(ICC)の所在地であるハーグで開催されたNATO首脳会議で、しかも国連憲章80周年の記念日の前日に、NATO事務総長は明らかに国際法に違反するイランへの軍事攻撃について、卑屈にも米大統領に祝辞を述べている。その一方で、ドイツ首相は「我々のために汚れ仕事を」してくれたイスラエルに感謝している」と厳しい批判を加えている。その上で、ロシアがNATOを攻撃した場合、トランプ政権下の米国がNATO条約5条に基づいて義務を履行するかどうかについて疑問を呈しつつ、主要加盟国であるはずの米国が、あろうことか加盟国カナダの独立と加盟国デンマークの領土保全(グリーンランドのこと)を公然と脅かしている事実について、首脳会議の議題にすら登らなかったことを鋭く問うている。また、「米国がもはや信頼できるパートナーではなく、同盟国の主要な利益に公然と反しているのであれば、欧州諸国はもはや米国から兵器システムを購入すべきではない」と指摘し、「欧州における米軍基地の存在についても再交渉が必要となる」とも述べている。これは、実は日本も真剣に考えねばならない問題なのである。
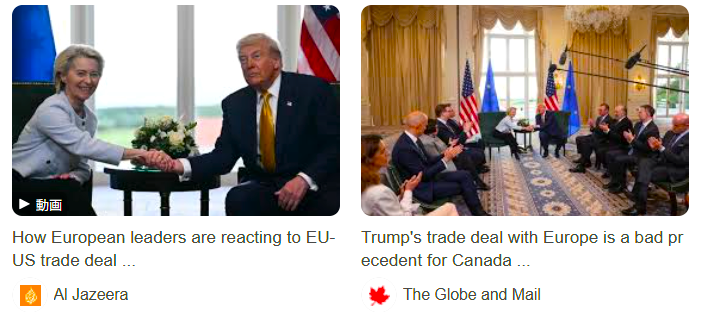
EU解体を狙うトランプ
「関税ハンマー」による脅迫で、EUもトランプの前に膝を屈した。EU委員長のフォン・デア・ライエン(目立ちたがり屋の元・ドイツ国防大臣)は、6月27日、スコットランドの有名なゴルフリゾート、ターンベリーでトランプと首脳会談を行った。EU委員長が、トランプのゴルフついでに、ブリュッセルから呼びつけられたのである。この会談場所の設定自体が、EUにとっては屈辱的なものだった。フォン・デア・ライエンは、引きつった笑顔でトランプと握手をして、たくさんのことを飲まされた。写真の背後に見えるのはゴルフ場である。
トランプはいかにしてブリュッセルを屈服させたかとして、「米国とEUの関税協定は戦争なき無条件降伏である」と、ロシアのメディアに書かれた。「アメリカは今後、自動車を含むEUからの膨大な輸入品のほとんどに15%の関税を課すことになる。鉄鋼とアルミニウムには現状の50%という関税が引き続き適用される。他方、米国にとっては、衰退しつつあるとはいえ巨大なEU市場での販売は、平均関税率ゼロか、せいぜい1%以下である。」
トランプ政権が「グレート・リセット」と名づけたシナリオは2つある。1つ目は「原点回帰」とされるシナリオである。その狙いは、「エリートの巣窟」であるEU委員会の権限を弱めること、EU法は加盟国の主権を超えない範囲に限定されること、EU議会の立法機能を剥奪し各国首脳で構成するEU理事会にすべての決定権を委ねることである。2つ目は、「新たな始まり」というシナリオである。現在のEUを解体し、さらに現行のさまざまな規制(移民・労働、LGBTなど)を撤廃して各国の主権を最重視することで、欧州統合路線を否定することである。この2つのシナリオは保守系「ヘリテージ財団」がトランプに提案した「プロジェクト2025」に含まれている(『選択』2025年8月号14-15頁)。前述のようにスペイン、ポーランド、ハンガリー、やがてはフランスやドイツ(AfD)なども親トランプに傾いていくのだろうか。先週、解体を狙う組織の長を、ゴルフリゾートに呼びつけて関税合意を強制したのである。このトランプの思想と行動はどこまで認識されているのだろうか。

石破首相はトランプにどう向き合うのか
NATOとEUがトランプに屈してきたが、日本はどうか。右の写真は、今年4月8日から12日まで、ルッテNATO事務総長が来日した際、国会周辺にかかげられた「街路旗」(NATO旗と日の丸)である。岸田文雄首相(当時)は、NATOの首脳会議に度々参加して前のめりだったが、石破茂首相は一歩引いたところがある。NATOのインド太平洋パートナーと呼ばれる日本、オーストラリア、韓国の首脳は、前述した6月のNATO首脳会議への出席をキャンセルした。ロシアのメディアはいう。「太平洋地域のリーダーたちの不在は、NATOの足跡の拡大に対する不快感の高まりを示唆している。多くの地域諸国にとって、NATOのアジアにおける存在は、安定ではなく、共有された安全保障の名の下に地政学的紛争に巻き込まれるリスクを意味する」(RT 2025年7月2日) と。
フランスの『ル・モンド』英語版6月26日は、トランプの予測不可能な政策に直面し、日本の指導者たちは米国への依存を減らすために、別の外交・安全保障戦略を策定する必要性を検討していると書く。その例として、石破首相が6月13日、イスラエルのイラン攻撃について「交渉が進行している間は容認できない」と非難し、英仏独のイスラエル支持の立場と「一線を画した」。6月21日の米軍のイラン核施設への攻撃に際しては「より慎重な態度をとり、双方に対話の再開を呼びかけ、その後、イランの核開発を阻止する必要性を「理解」していると述べた。そこで想起されるのが、2003年3月のイラク戦争開始時のことである。ブッシュ政権による国際法違反のイラク攻撃について、小泉純一郎首相(当時)は、間髪を入れず、「理解」のみならず「支持」までも表明してしまった。『ル・モンド』もいうように、石破は英国などとは「一線を画した」わけで、これは微妙な距離感だった。
米軍の核施設攻撃の直後に、イラン国会がホルムズ海峡の封鎖を承認したと報じられた。日本は原油の8割をこの海峡を通って輸入している。もし、ホルムズ海峡封鎖となれば、かの安倍晋三が9年前に語っていた「存立危機事態」が浮上してくると思ったが(直言「「戦争の惨禍再び」―ホルムズ海峡「存立危機事態」?」)、石破首相は「最大の緊張感を持って注視をしてまいりたい」と述べただけで、その後はほとんど触れなかった。
私は石破首相について、直言「軍事的合理性にこだわる首相の誕生」で書いたような危うさは持ちつつも、安倍晋三や高市早苗のような、思想性のない右翼政治家とは異なり、石橋湛山と田中角栄を尊敬する「不器用な政治家」と評している(『毎日新聞』2024年12月3日)。
トランプの「関税ハンマー」に石破首相はどう対応しているのか。まだまだ隠された部分がある。文書に残さなかったのも不可解だ。「合意」をめぐっては、虚偽表示や錯誤、強迫、あるいは心裡留保が複雑に絡み合って、まともな関税合意になっていなかったのではないか。関税率が15%未満の品目が一律15%になり、15%以上の場合は上乗せされずに従来の税率が維持されるという「口約束」に基づく希望的観測は打ち砕かれた。 「格下の格下」(赤沢亮正経済再生大臣)を「逐次投入」して交渉モドキを続けてきたことのツケは、7日に早くも明らかになった。米国が課す「相互関税」に関する米連邦官報の記載をめぐり、日本政府の説明との食い違いが表面化している。訪米中の赤沢大臣が修正を迫るといわれているが、too lateになりそうである。
石破自身がトランプと向き合って、半年前のこの顔ではなく、「なめられてたまるかぁ」の意気込みで臨むことができるだろうか。相手は「恣意の支配」を体現したリヴァイアサンⅡである(直言2020年12月28日参照)。
【文中敬称略】
トップページへ