近年、この業界では、9年連続「視聴率四冠王」だった日本テレビが勢いを失っているという。「ドル箱」の巨人戦中継の低迷が原因だそうである。今年3月28日の開幕戦の視聴率は16.2%で、史上最低。視聴率は10%が精一杯で、2割を超えることはなくなったという。他方、6月27日の横浜対阪神の試合は、今季最高の平均24.9%を出したそうである。テレビをあまりみないし、ひいきのチームもなく、野球界に唯一「軍」を保持する新聞社のチームさえ勝たなければ、どこが勝ってもいいという「消極姿勢」が私の立場である。だから、阪神がリーグ優勝した今シーズンは実に気分がいい。ちなみに、85年の阪神優勝のことは、「保革伯仲」(もはや死語)の政治にひっかけて、『法学セミナー』1986年4月号の「憲法と政党」という小論のなかで触れたことがある。
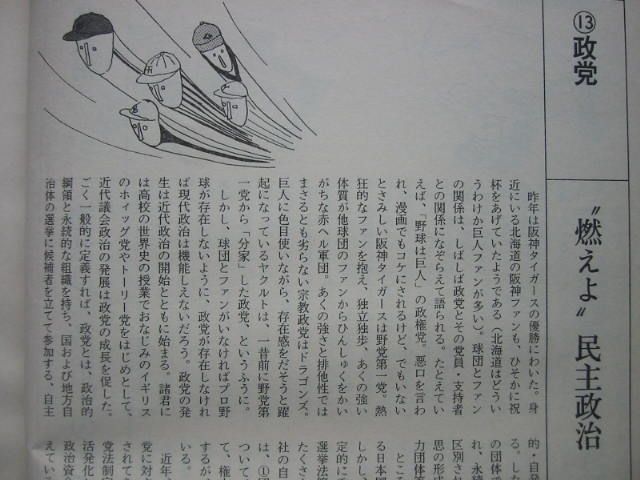
ところで、視聴率を稼ぐため、ダイエー監督の顔をトイレにするというネタで批判を浴びたフジテレビ。この局は好みではないが、例外的にみていたのが「北の国から」であった。このドラマは必ず高視聴率がとれた。視聴者をなめてはいけない。やはり多くの人が注目し、評価する番組は存在するのだ。率(量)より質。つまり「視聴質」である。この言葉は、朝のワイドショー「とくダネ!」の司会者、小倉智昭さんから直接聞いたことがある。
1992年12月14日。文化放送(ラジオ)の「小倉智昭の夕焼けアタックル」という生番組に呼ばれて、拙編著『きみはサンダーバードを知っているか』(日本評論社)について25分間話す機会を与えられた。番組には「小倉ミシュラン」というのがあって、「PKOよりサンダーバードがすぐれているベスト5は?」という形で、小倉さんが拙著の主張をわかりやすく紹介してくれた。番組の冒頭、小倉さんは、「今回はちょっと固いテーマだが、これからは視聴率よりも視聴質が大切になる。真面目な番組がもっと増えていい」という趣旨のことを語った。そばで聞いていて共感したのを覚えている。10年あまり前の話だが、その後も視聴率競争はとどまるところを知らない。視聴率競争の結果、地味で良心的な番組がずいぶん消えていった。テレビ朝日系列の「ザ・スクープ」もその一つ。日テレ系で深夜やっている「ドキュメント2003」。毎回はみていないが、「ドキュメント88」なんて頃からビデオに撮り、授業で使ったこともある。日テレのこの番組は、視聴率だけで判断すればとっくに消えている。ずっと続いているということは、テレビの現場でがんばっている人々がいるということだ。
「率」を競う傾向は、教育現場でも目立つ。最近、東京のすべての都立高校(207校)が、進学などについて「数値目標」を掲げるに至った(『読売新聞』2003年9月8日付)。例えば、日比谷高校の目標は、東大現役合格20人以上、早慶上智100人以上だそうだ。一方、都立西高は大学名をあえて入れなかった。校長は、「東大や京大に入れる学力があったとしても、進学先は生徒自身が決めること」という。都立国立高校(私の母校)は「難関国公立大合格150人(うち東大20人)」だそうだ。校長いわく。「予備校のような目標を掲げることに、教師の間で消極的な雰囲気があったが、もはや悠長に構えていられない」。このコメントに続けて記者は、「同校が、都立高の野球部として初めて甲子園に出場した1980年度の東大合格者は39人」と書いている。23年前の夏、強豪・箕島高校(和歌山県)に一回戦で敗退したものの、後輩たちの活躍は私の心のなかに熱く残っている。それにしても、現在の校長のコメントは何だろう。OBとして情けない。せめて西高の校長くらいのことはいえなかったのか。
1969年高校紛争を体験した者としては、大学入試一辺倒ではない高校生活が理想だった。当時の校長も教師も立派だったと思う。生徒の声に耳を傾け、入試には直接関係のないような、英会話や日本史講読(邪馬台国史料研究。これが面白かった!)の選択科目を新設し、大学のゼミのような雰囲気をつくり出した。日本史の教師も生き生きと授業していた。30年以上たって、「目標、東大20人!」と貼りだす(?)ような母校の状況を聞くと、「なぜ、そうまでして、せかせかと成果を競うのか」と思わざるを得ない。
いま、世の中で「改革」と名のつくものは、「誰のため」という点でみると、首をかしげるものが少なくない。「小泉改革」がこの国の人々の心に植えつけた最悪の「記憶」は、社会のあらゆる分野における、「せかせか」感ではないか。
「遠山プラン」だの「トップ30」だのと、さして多くもない予算を使って、全国の大学に「せかせか」感を蔓延させている。この官僚女性文科相の時代というのは、大学と「大学の自治」にとって最悪な時期として歴史に記憶されるだろう。私は「せかせか」に巻き込まれないために、公的資金には応募せず、研究に必要な経費は自力で稼ぐことにしている。私の「無意味で(公的基準から見れば)不気味な資料」を公金(補助金)で買うのは困難であり、それを説明する書類をつくる時間があったら、別の原稿を書いた方がいいという考えからだ。資金(手段)を獲得して、それに合わせた研究(目的)を、決められた期限内(年度内)にやるという「せかせか」感から免れたい。私自身がせっかちな性格なので、パソコンで原稿を書かないこととあわせて、マイペースを守っている。人生で使える残り時間の有効活用という観点から、学会や研究会も必要最小限度にして(各方面への不義理をお詫びします)、仕事量も限定してきている。その内容やスケールは足元にも及ばないが、養老孟司氏の主張と生き方に共感するところ大である(「『公』頼まず『個人』で研究」『東京新聞』03年4月22日付文化欄)。
ところで、世間では大学へのバッシングが強まっている。演出された面があることも否定できないが、実際に大学には、世間・マスコミから批判を受ける面がいろいろと存在することは否めない。ただ、大学固有の事情を無視した一方的批判は、大学の自由な雰囲気を奪う方向に作用することを知るべきだろう。例えば、「第三者評価」や「学生による授業評価」が称揚されているが、その行き過ぎがもたらすマイナス面への自覚は存外乏しい。「学生=消費者」という考えがある。例えば、製品に対する消費者のクレームを次々と公開した場合、なかには勝手な思い込みや勘違いも含まれている。「学生による授業評価」(学生自治会による)にも罵詈雑言に近いものも掲載されたことがある(近年はだいぶ改善されたが)。たまに授業に出てきた学生が、「一年中、平和主義ばかりやっている。まともな憲法の講義をやれ」なんて書き込む。実際は、24回やった憲法講義のうち、平和主義はたった1回だった。1回しか出席しないで勝手を書く不心得者の声も、授業評価の一部として紹介され、読者に「そういう評価もある」と印象づける。フェアではない。教員はいろいろ苦労と工夫を重ねて授業運営を行っているが、ほとんど授業に出てこない不心得者の意見も調査時(たいてい、その授業の最終日。だから試験の範囲確認のため多く出席する)に拾われ、それが「消費者」の正当な声として扱われる。私は、一般に授業評価自体は必要だと思っている。昔のように、教員がノートを読み上げるだけという悲惨な授業は存在しえなくなった。ただ、じっくりと、ボソボソと、しかし誠実に懸命に講義する教員に対しては、「何をいっているのかわからない」という声が拾われ、そのまま否定的に紹介されてしまうのは問題だろう。地味な講義でも、1年受講したら、その先生のよさがわかり、学問の面白さを感じたということもある。教室では、学生にも努力が求められているのだ。テレビの解説者みたいな、軽快なテンポと「一見わかりやすい」授業ばかりになったら、その方がむしろ不気味である。一律の授業評価は、いま、大学のあり方に深く、かつ大きな影響を与え、それは決してプラスの効果だけではなく、大学にとってかけがえのないものを失わせ、傷つけているのではないか。
なお、「何をいっているのかわからない」という学生の声について付言すれば、これには、①教員の表現力の問題、②学生側の理解力の問題、③私語が多くて聞き取れないという三つの問題が重なっている。「何をいっているのかわからない」という意見は、もっぱら①として印象づけられる。②と③は学生側の問題であり、自分の怠惰を棚に上げて、もっぱら教員を非難する声を紹介するのは問題だろう。最近、学内非常勤で担当している政経学部の前期試験の答案を採点していたら、「後ろに座ると私語で先生の声が聞きとれないので、もっと大きな声ではっきりと話してください」という感想が複数あった。ここまできたか、と驚愕した。私の声は大きくて、はっきりしているという評価を得てきたので、こういう感想は生まれて初めてだった。細長い大教室に580人がびっしり詰まって授業をやっているので、教壇から遠い後方の学生の顔はまったく見えない。たまたまその周囲に座った学生の話では、そこは前方とまったく違った世界になっているという。たまに注意するが、いっこうに静かにならない。大学教師20年の間に、北海道や広島で非常勤講師をやったが、私語が多いといわれた大学(「偏差値」は高くはない)で、私語なしの教室をつくってきた私としては、最近の高偏差値学生の荒廃には目を覆うばかりだ。もちろん、大半の学生たちは熱心に講義を聴いてくれている。鋭い質問をメールで送ってくる学生も少なくない。だから、この学部の授業を私はむしろ喜びとしているほどだ。でも、私語する学生たちも授業評価に参加して、勝手な評価を書き込むわけである。「学生による授業評価」の過大評価が禁物である所以である。
加えて、評価の基準にも問題がある。「板書をきちんとしているか」「教科書の使い方はどうか」「授業は計画通りに進行しているか」といった設問があり、それが点数化されている。だが、教員の授業は千差万別だ。思わぬ脱線から、予定外のテーマを話すこともある。その意外性が授業のライブ感覚と面白さの根源だと私は考えている。きちっとやるだけなら、教科書を読めばよい。また、板書をしないことは必ずしもマイナスにはならない。私はあまり板書はしない。話の流れを崩したくないというのが大きい。ポイントなる言葉はゆっくり強く発音し、かつ繰り返しいうようにしているので、学生は自分の判断でメモをとるべきだろう。わかりにくい単語だけは、黒板に書くようにしている。教科書にあることまで板書して箇条書きにする必要はないし、時間の無駄だろう。講義は、教員の考えや発想、体験などを生で感じ取ることを大切にしたい。「板書をきちんとしているか」なんて質問をすると、私の場合は点数がグッと低くなる。授業の改善も多様であるべきだろう。そうでないと、「学生による授業評価」の先には、意図するしないにかかわらず、八方美人的で、刺激の少ない、均質的な授業がくるおそれがある。だから、授業評価はむずかしい。
来年4月から国立大学が独立行政法人化される。大学は効率性と迅速性が競われ、画一的になっていく。新しいサービスがどんどん増えて、教職員の負担も急増してくる。新しいサービスの一つに、授業をインターネットで流すという試みがある。2年ほど前、複数教員で担当する授業をインターネットで流すためにビデオ撮影をされたことがある。事務局から「カメラの関係で教壇からあまり動かないでください」という指示がきた。私は教壇の周囲を左右に、時には上下と動きまわって話をする。その日は指示を意識して、表情はいつもよりも硬かった(と自分では感じた)。オンデマンドという方式が普及しつつあるが、人間のぬくもりが失せたインターネット授業よりも、教員と学生の呼吸と鼓動が感じられる古典的で素朴な授業の方式を大事にしたいと思う。
サービスをすることは大切だ。大学はある意味ではサービス機関である。それもよしとしよう。「学生のための大学に」。それもいい。だが、いつの間にか、「何のために学問をするのか」という点が、当事者のなかに希薄になってきたのではないだろうか。これは恐ろしいことである。サービスの過剰・過多、サービスの先取り・先回りは、少子化が進む市場で勝ち抜くという目標には有効かもしれないが、学問の発展にとって「毒まんじゅう」になる可能性もある。視聴率と授業評価。「毒」はすでにかなりまわっているように思う。いずこでも、本当に大切にしなければならないものは何かを見極めていかないと、その先にあるのは学問と文化の荒野だろう。