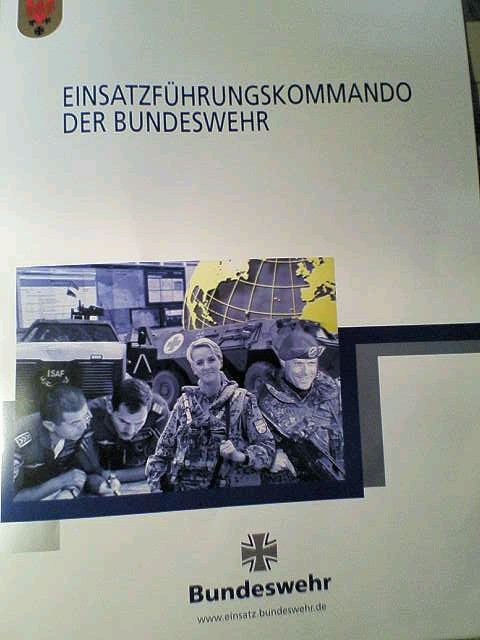 ちなみに、ドイツはアフガニスタン、レバノンなど全世界に、7700人の兵員を展開している。派遣軍司令部は、古都ポツダム郊外にある、連邦軍派遣軍司令部である。ここで、すべてのミッションの指揮がとられる。プロイセンの軍都ポツダムに、このような司令部を置いたのは何とも象徴的である。写真は、派遣軍司令部の最新パンフレットである。アフガンで勤務する女性兵士の姿もみえる。
ちなみに、ドイツはアフガニスタン、レバノンなど全世界に、7700人の兵員を展開している。派遣軍司令部は、古都ポツダム郊外にある、連邦軍派遣軍司令部である。ここで、すべてのミッションの指揮がとられる。プロイセンの軍都ポツダムに、このような司令部を置いたのは何とも象徴的である。写真は、派遣軍司令部の最新パンフレットである。アフガンで勤務する女性兵士の姿もみえる。明日は「9.11」の6周年である。「その日」は、集中講義で大阪に滞在していたときだったので、いまも記憶は鮮明である。ブッシュ政権は、「これは戦争だ」といってアフガニスタン侵攻を開始した(2001年10月7日)。だが、これはまったく間違った対応だった。
自衛権行使は外部からの「武力攻撃」に対して行われ、攻撃主体は国家(軍隊)の場合である。「テロリスト」は国家機関ではない。そこで、個々のテロ行為でも、国家による「武力攻撃」と同程度の効果を発生するような場合には、それを国家による「武力攻撃」に準ずるものとみなして、自衛権の発動を正当化する議論がある。イスラエルや米国の一部でしか支持されていない、かなり乱暴な議論である(「事態の累積理論」)。この議論でも、国家が「テロリスト」に何らかの形で関与していることが前提とされる。具体的にいえば、資金や活動拠点の提供などによる「直接的関与」。警察力が弱くて、「テロリスト」の活動を十分に抑止できないような国もまた、「間接的関与」と評価され、自衛権行使の対象となりうる。ここまで広げる、かなりアバウトな議論といえる。
アルカイダの拠点を自国内に置かせていたタリバン政権に対して、米国はこうした論理に乗って攻撃を仕掛けたわけである。こうした米国に対して、NATOは、創設以来初めて、「同盟事態」(条約5条)を宣言。集団的自衛権行使モードに入った(10月2日)。NATO条約上の本来の手続からすると、かなり無理な認定だったのだが。
いうまでもなくテロは犯罪であり、それに対処するのは本来、警察の仕事である。もし(これはブッシュ政権の本質からしてあり得ない「歴史におけるif(もし)」ではあるが)、あの時、米国が、アフガニスタンへの軍事行動を行わないで、世界に向かってテロを糾弾し、国際刑事警察機構(INTERPOL)を軸に、法に基づいた真相の究明と、計画・実行者の逮捕・処罰を呼びかけていたら、その後の展開は違ったものになっていただろう。事件当日、アラファトPLO議長(当時)が献血に応じて、ニューヨーク市民への連帯を表明するニュース映像は、強く印象に残っている。イスラム諸国も、国際刑事警察機構の協力要請に応じて、被疑者逮捕に協力さぜるを得なかっただろう。そして、「9.11」の翌月に行われた国連の会議で、「テロの定義」が明確に行われていたならば、その後の国際社会はテロとの関係で違った歩みをしていたに違いない。足を引っ張ったのはここでも米国とイスラエルである。「味方にできなくてもいいから敵にしない」どころか、「味方にできる人までも敵にする」ブッシュ政権の「対テロ戦争」は、本来のテロ対策とは無縁の、「明後日の方向」へと暴走している。
日本では、「9.11」4日後の9月15日、「ショー・ザ・フラッグ」(Show the flag)という言葉が突然メディアに流れる。米国務副長官が柳井俊二駐米大使(現在、集団的自衛権行使容認の報告書をまとめている「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」座長)に対して使ったというのだが、後に、日本側から「いわせた」のではないかという疑問も出てくる、いわくつきの言葉だった。「旗を見せろ」はやがて「日の丸を見せよ」にかわり、数日のうちに、「インド洋上で護衛艦の日の丸を見せよ」へと「意訳」されていった。
護衛艦派遣に法的根拠を与えるべく、「平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」(2001年11月2日、法律第113号)が、提出から2週間で成立する。「湾岸を繰り返すな」という「作られたトラウマ」がこれを加速した。当時、海上自衛隊はイージス艦の派遣にこだわった。首相官邸や政治レヴェルの力学が働き、最終的に、通常型護衛艦と補給艦の派遣に落ちついた。
6年が経過して、世界も米国内でも、ようやく冷静な眼差しが生まれ、「9.11」についてのさまざまな疑問がメディアにも登場するようになった。マイケル・ムーア監督作品「華氏911」は、その疑問をわかりやすく(かなり強引に)提示する一例である(なお、先週観た同監督作品「シッコ」では、後遺症に苦しむ消防士ら〔「9.11の英雄」〕の姿が痛々しかった)。私は単純な「陰謀説」はとらないけれども、この事件の背後には、きわめて複雑な要素や力学が絡み合っていることは間違いない。先週、『9.11事件は謀略か』(デヴィッド・レイ・グリフィン著=きくちゆみ・戸田清訳、緑風出版)という本を読んだ。奥付には、2007年9月11日発行とある。ブッシュ政権の「共犯性」を示す「40の証拠」を挙げながら、政府の説明の矛盾点を執拗に衝いていく。著名な国際法学者リチャード・フォークが序文を寄せている。フォーク教授が書いているように、「特に戦争と平和の問題においては、〔政府が〕大衆の意見を操作してきた長い歴史がある」ことを十分に踏まえる必要があり、「9.11」におけるブッシュ政権の説明をそのまま信ずるのは「政治的無邪気さ」(フォーク)というべきだろう。そして、この6年間を省みれば、あの事件で最も利益を得たのが誰であるのかが明らかになってくるように思う。
冷戦構造が崩壊し、巨大な軍事力を維持し続ける上での「わかりやすい脅威」(旧ソ連のような)は存在しなくなった。91年湾岸戦争以降、「ならず者国家」や地域紛争などの「小粒な脅威」では、軍需産業の「未来」は安定しない。大規模な軍の転換や、高額なハイテク兵器の購入を正当化できる、「パンチのある理由づけ」が求められていた。その意味で、「9.11」は、冷戦後の平和・非軍事的なパワーの増大・強化に危機感をもった勢力にとって、まさに「王政復古」ならぬ「軍事復古」のための大逆転劇だった。
その点、ラムズフェルド前国防長官は正直である。「9.11」の1カ月後の『ニューヨークタイムズ』紙(10月12日付)で、「9月11日は世界を作りかえるために、第二次大戦が提供したような種類の絶好のチャンスをつくりだした」と語ったという(前掲書250頁)。実際、米国の軍事費は、2001年度は2800億ドルだったが、この事件の翌年、一気に480億ドルも増額される。「対テロ戦争」の必要性から毎年増えつづけ、2006年度には5200億ドルに達する(同246頁)。財政緊縮のなかでの予算倍増である。「9.11」のおかげで、軍や軍需産業にとっては、夢のような状況が現出したわけである。
他方、「9.11」の首謀者とされるオサマ・ビン・ラディンは「泳がされ続け」、生死は不明である。「存在しなかったら、彼を創り上げる必要がある」(ジョージ・モンビオット)ともいわれている(同214頁)。
「対テロ戦争」という「明後日の方向」への暴走の結果、アフガニスタン民衆の犠牲者は増えるばかり。他方、外国軍隊の駐留への反発から、旧タリバン勢力の復活も著しい。テロの根源をなくすこともできず、テロの温床はむしろ強化・拡大している。
さて、今年11月1日、テロ対策特措法の期限が切れる。この法律が登場したとき、『朝日新聞』2001年10月10日付「オピニオン欄」で、私は、特別措置法(特措法)という法形式を批判した。その後、『法律時報』2002年1月号でも論じたので、法律の細かな問題はここでは触れない。ただ、「何が何でも活動継続」(高村防衛相インタビュー『読売新聞』9月5日付)という立場でいいのだろうか。産経新聞社とFNNの合同世論調査の結果でも、国民の54%が延長に反対している(『産経新聞』8月30日)。特別措置法は当初は期限2年で延長ありだった(附則)。その後3度も延長されている。特措法という法形式に鑑みれば、延長の繰り返しは、実質的な恒久法化をはかるもので、立法の作法に反することは明らかである。これ以上の延長はあり得ない。修正して延長するということも許されない。なぜか。テロ特措法とそれに基づく自衛隊の活動には、少なくとも重大な問題が二つある。
第1に、洋上給油の実態である。安倍首相は「洋上給油の継続は、対外的な公約」とまで語った(9月9日付各紙)。APEC首脳会談の合間に行われた日米首脳会談(9月8日)の際に、ブッシュ大統領から洋上給油の継続を要請されるや、「対外公約」とまでいってしまう。そこには、何らの「戦略」なしにブッシュ政権に追随する、「米国=国際社会」という狭い視野しかない。
そうしたなか、メディアでは、洋上給油の中身が問題とされるようになってきた。江田けんじ衆議院議員によると、「米海軍中央司令部&第5艦隊」のホームページにある「イラクの自由作戦」の「有志連合の貢献」という項目には、「日本政府は、不朽の自由作戦の開始以来、8662万9675ガロン以上の燃料(7600万ドル以上に相当)を貢献した」と書いてあるという(アクセスしてみたが、米軍が削除したのか、当該記述は確認できない)。1ガロンは3.785 リットルだから、約32.8万キロリットルになる。日本政府は、これまでに38万キロリットル(約220億円、07年7月現在)の艦船用燃料を給油したとしているから、その85%がイラク作戦にも使われた可能性があることになる。もともと洋上でのこと。米軍艦艇の活動がアフガニスタンでのそれに限定されるという保証はないし、メディアも確認は困難である。江田氏がいうように、第5艦隊の担任海域からすれば、アフガニスタンとイラクの両作戦は、この海域では一体化しているとみるのが妥当だろう。となると、そうした艦艇の燃料を、「テロ対策特措法」を根拠にまかない続けるのは筋が違うし、法律(本特措法)の目的とも整合しない。端的にいえば、アフガニスタンやイラクで行われている米軍や有志連合軍による民衆の殺戮に、ひたすら「油を注いでいる」のが日本ということになる。洋上給油を直ちにやめなければならない理由がここにある。
第2に、テロ特措法延長問題の背後には、単なる給油活動の「延長」にとどまらない問題があることを見逃してはならない。最近、元海幕長は、洋上給油から「哨戒活動」への移行を検討すべきだと主張している(『東京新聞』8月21日付連載「新防人考」〔半田滋記者〕)。「9.11」後のわずかな期間で制定されたこの法律の狙いが、前述したように海自イージス艦をインド洋に派遣することだった。政治的な妥協で、洋上給油という形に落ちついたが、この活動は、ブッシュ政権にとっては、単なる燃料費の節約にとどまらない「利益」を生んでいる。
NHKラジオ第一放送「新聞を読んで」でも紹介したが、キャンベル米元国務次官補代理は、インド洋の自衛艦のプレゼンスは、石油資源を求めて進出する中国への抑止になるという認識を示した。海上自衛隊の側でも、「洋上の無料ガソリンスタンド」という自虐的な表現をしないですむような、「普通の海軍」らしい活動に転換していくという「本音」も出てきた。これは「テロ対策」とはまったく異なる筋のものである。「海上阻止行動」にイージス艦を派遣するのは、アフガンへの武器密輸などをチェックする目的にとどまらない。キャンベルがいうような、対中国、さらには海洋戦略としても、イージス艦をもつ海上自衛隊の運用思想は、「専守防衛」とは大きく異なるものに変質しつつある。この点を見過ごすことはできない。テロ特措法の延長がだめならば、将来企図されているのは、本格的な(イラク特措法も包括した)「自衛隊海外派遣恒久法」制定だろう。それは「専守防衛」を建前とする「自衛隊」というコンセプトからの離陸を意味しよう。
いま、当面やるべきことは、「9.11」直後の応急的対応の必要性はもはやなくなったという確認をして、テロ特措法を廃止すること。そして、インド洋上の海自部隊を速やかに撤収させる。その上で、米国の軍事戦略との絡みではなく、真のテロ対策やアフガニスタン再建への協力に日本の施策を切り換えることである。
そこで参考になるのがドイツである。実は、ドイツも日本と同じ悩みを抱えている。ドイツの場合、三つの派遣形態で、日本よりも深入りしてしまっている。
第1に、NATOの国際治安支援部隊(ISAF)として、3000人を、比較的安定したアフガニスタン北部に展開している。NATO部隊2万人のうちの15%を占める。国連安保理決議1386号(2001年12月20日)により、国連和平活動を支援するという建前である。このISAFの委任は、今年10月中旬で期限がくる。
第2に、トルネード戦闘機(偵察仕様)6機(要員500人)を、今年4月はじめに、アフガニスタン北部のマジャリシャリフに派遣したものである。警戒監視が任務とされるが、その派遣の議会承認に際しては、与党から69人の反対が出た。ISAF活動の支援という面と、下記第3の活動である「対テロ戦争」のため、タリバンの位置を米軍攻撃機に教えるという役割もある。この委任の期限も10月中旬である。なお、マジャリシャリフは、米軍の黙認のもと、北部同盟がタリバン捕虜などを大量に殺害した事件が起きた、いわくつきの場所である。かつて直言でとりあげたこともあるが、記憶している人は少ないだろう。
第3は、「不朽の自由作戦」(OEF)の枠内で、陸軍のエリート特殊部隊(KSK)100人を派遣している。これは「対テロ戦争」のコアへの参加となる。民間人の犠牲者が増えるに従って、この戦闘部隊の行動に対する批判・反発が高まっている。米軍は、ISAFとOEFの活動をドイツのように使い分けておらず、一体で運用しているふしがある。タリバン掃討作戦のような戦闘出動をISAFにおいてドイツ軍はやらない。やっているとすれば、この第3カテゴリーのKSKである。今年11月15日で派遣終了となるか。すでに終了の意見は、与党内(SPD)にも高まっているという。
関連して、「アフリカの角」において、ドイツ海軍は艦艇1隻(260人)が多国籍艦隊に参加している。紅海からアデン湾、アラビア海を経由してホルムズ海峡に至る海域の監視を行っている。海上自衛隊補給艦はこの艦隊にも洋上給油を行っているようだ。
先週の9月5日、ドイツ政府は、アフガニスタンの民生部門の復興に関する協力にシフトする方針を閣議決定した。2010年までに、8億8500万ユーロ以上を復興援助に支出する予定である。2007年には、8000万から1億ユーロに援助を増額する。そして、2008年度は1億2500万ユーロへとさらに増額する。人道援助の枠内では、ドイツは2001年以来、7300万ユーロ以上を支出してきた。
2002年4月には、アフガニスタン警察の養成・強化に指導的役割を引き受けた。39人のドイツ警察官が、4860人の現地の警察官を養成した。専門的に継続的に教育したのは14300人である。カブールの警察大学校の建設はドイツの重要なプロジェクトの一つである(Die Welt vom 5.9.2007)。年間、約1200万ユーロが警察検察においてドイツ側から投入されている。連邦軍の派遣もある情勢が落ちつくまでとし、その後は民生分野への支援を強化していくようである。
なお、野党の緑の党は、4日、アフガニスタン派兵をめぐって分裂した。ISAFの活動には賛成でも、トルネード派遣については反対が強い。「不朽の自由作戦」の特殊部隊派遣についてはより明確な反対が出そうである。特に、「対テロ戦争」との関係での上記3番目のミッションの期限である11月15日が近づくにつれて、議論が分かれてくるだろう。ドイツのある新聞は、この「11月15日」をめぐり、「同意作戦」(Operation Zustimmung)というタイトルの評論を出し、「対テロ戦争」をめぐるドイツ政治の複雑な事情を探っている(Frankfurter Rundschau vom 6.9.2007)。
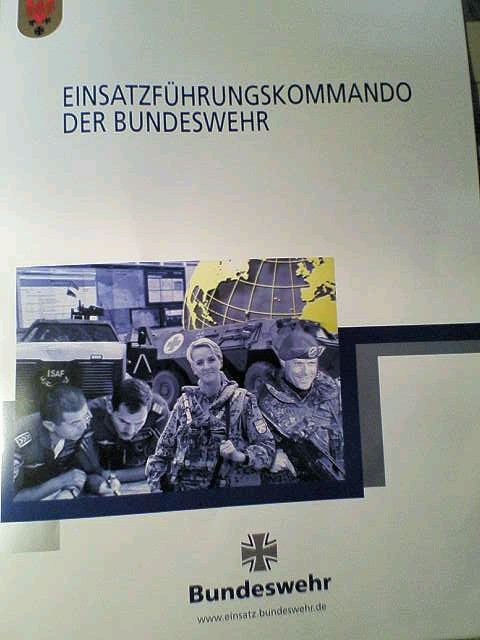 ちなみに、ドイツはアフガニスタン、レバノンなど全世界に、7700人の兵員を展開している。派遣軍司令部は、古都ポツダム郊外にある、連邦軍派遣軍司令部である。ここで、すべてのミッションの指揮がとられる。プロイセンの軍都ポツダムに、このような司令部を置いたのは何とも象徴的である。写真は、派遣軍司令部の最新パンフレットである。アフガンで勤務する女性兵士の姿もみえる。
ちなみに、ドイツはアフガニスタン、レバノンなど全世界に、7700人の兵員を展開している。派遣軍司令部は、古都ポツダム郊外にある、連邦軍派遣軍司令部である。ここで、すべてのミッションの指揮がとられる。プロイセンの軍都ポツダムに、このような司令部を置いたのは何とも象徴的である。写真は、派遣軍司令部の最新パンフレットである。アフガンで勤務する女性兵士の姿もみえる。
タリバンとの戦闘も激化している。アフガン民衆の犠牲者の数は増える一方である。劣化ウラン弾の影響など、今後も犠牲者は増えていくだろう。ドイツ兵の派遣先での死者数も急増している。この点で、『朝日新聞』の連載「『戦わない国』は」(5)〔松井健記者〕は重要な情報を含む(8月16日付東京本社版の見出しは「増える犠牲、兵士に迷い・ドイツ軍派遣」、同日の大阪本社版は写真入りで、「『人道支援』続く犠牲・ドイツの派兵」)。この記事は、私もドイツ滞在中の9月11日に取材したことのある連邦軍協会(Bundeswehrverband)が行ったアンケートを紹介しながら、「海外派遣の意義と目的について十分に説明を受けていない」という兵士が6割にのぼると指摘する。「海外派遣が社会から支持されている」と回答したのは1割だった。海外派遣への疑問は底辺と末端から広がっている。「人道支援だと言われて行った場所で、なぜドイツ兵が命を失うのか」。これはアフガンで自爆攻撃により負傷・除隊した元上級曹長の言葉である。
ドイツは、イラク戦争では米英と一線を画した。イラク戦争に向かう時期、ドイツ政府は国際法違反の戦争には、在独米軍基地使用を認めないという強い姿勢もちらつかせた。「対テロ戦争」では「限りなき連帯」を表明したものの、いま、アフガニスタン紛争への関与をめぐり、微妙な距離をとりつつある。
さて、本日、参議院で与野党が逆転して初めての国会が始まる。民主党・小沢一郎代表の延長反対の強い姿勢に対して、政府・与党は、特措法延長は無理とみて、最初からインド洋での給油活動だけに絞った法案を準備中という。民主党はこの提案に簡単に乗ってはならない。むしろ、民主党案がいうように、アフガニスタンへの復興援助のやり方を見直し、本格的な社会的構造整備のための支援に転換することである。警察の強化の提案も重要である。ドイツがすでに行っているが、アフガニスタンにおける法整備や法執行機関をまっとうなものにしていく意義は大きい。お金だけでなく、警察官養成のプロを派遣することも有効な手段のなかに含まれる。
いずれにしても、6年前の「9.11」の前提にさかのぼった、根本的な議論、「テロ対策」という目的とそのために必要な手段の関係を冷静に検証する、そもそもの議論が求められている。